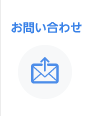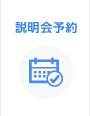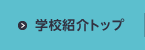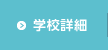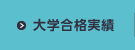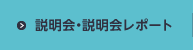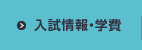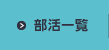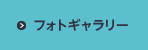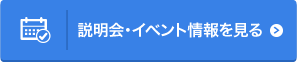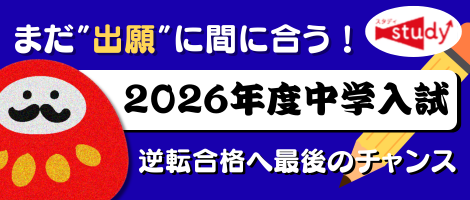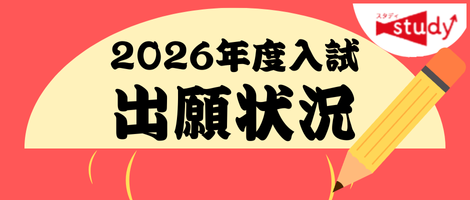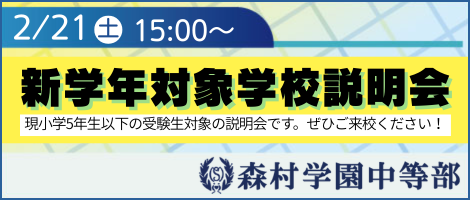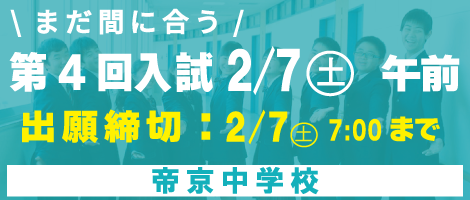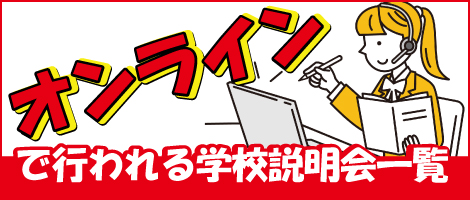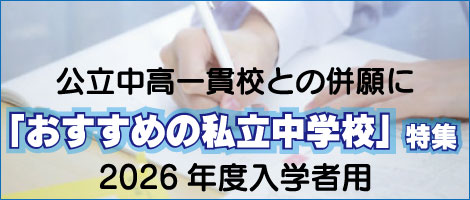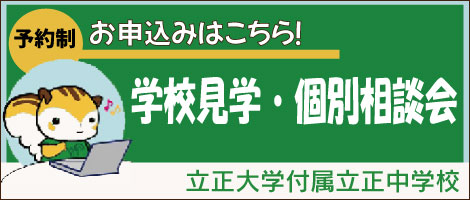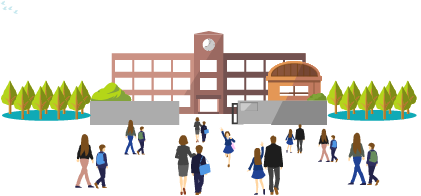学校詳細
建学の精神、教育理念
自立自存・寛容と共生・地球感覚
大妻多摩中学校は、1994年に開校した。大妻学院は1908年に学祖大妻コタカが裁縫と手芸の私塾を開設したことから始まり、当初より女性の経済的自立を促すためのキャリア教育に焦点を当てていた。大妻多摩中学校はその意思を引き継ぎ、女性が社会でキャリアを持つことによる経済的自立・社会的自立・人間的自立を達成するための教育を実践している。
同校の教育理念は「自立自存」「寛容と共生」「地球感覚」。「自立自存」とは、学祖大妻コタカの言葉で、主体的に考え判断を行い、自主的に行動する力を養うこと。「寛容と共生」は、多様性の時代、様々な価値観を持つ人への理解を深め、相互で連携して協働すること。「地球感覚」は、地球規模の視野で物事を見つめ、よりよい世界を作るために自分のできることを考え実行していくこと。
この3つの教育理念を生徒一人一人が具現化するために、「わたしの力を、未来のために」というスローガンを掲げている。生徒が社会でキャリアを持つ際に、他者(=社会・未来)のために貢献できるようになることを促すためのものである。そしてこれは大妻多摩の目指す経済的自立・社会的自立・人間的自立の意味でもある。
教育の特色
独自の教育カリキュラム「Tsumatama SGL」
大妻多摩中学校には、独自の教育カリキュラム「Tsumatama SGL」がある。Sは「Science科学教育プログラム」Gは「Global国際教育プログラム」、Lは「Liberal Arts教養教育プログラム」だ。
「Science科学教育プログラム」は、まず算数・理科の面白さを伝える学習を行う。数学では教科書に沿った授業を行いつつ、数学の理論が社会でどのように適用されているのか実例を知る。例えば三角比を利用して校舎の高さを測量するなど、実用的な理解を促している。理科では数多くの実験を行うことで教科書の内容をより詳しく理解するような仕組みが多い。5つある実験室で、4種類の顕微鏡や実験器具が生徒一人1セット利用可能な環境で、中学1年から高校3年まで実験を行うため、生徒は中1の段階で全員白衣を購入することになっているほどだ。これらの科学教育プログラムの成果により、理系を選択する生徒は中学開校以来4割程度を維持し、時には5割を越えることも。
「Global国際教育プログラム」は、中高一貫6年間の教育で、国際人としての基礎を身につける。英語の授業は5ラウンドシステムを導入。中学3年間で聴く力と話す・発表する力をトレーニングしていく。中1では立川にあるTGGで半日英会話体験を実施。中2秋には「グローバルインタラクションチャレンジ」という名称で3日間英語漬けになるプログラムを学校で実施。生徒をランダムに6~7名にグループに分け、1グループに1名ネイティブ教師をつけて授業を展開。
また、中学3年で、グローバル・キャリア・フィールドワークというオーストラリアへの修学旅行を行う。キャリアという言葉があるように、語学研修が目的ではなく、キャリア教育の一環として行われており、同校の姉妹校の学生たちとの交流、大学のキャンパスツアー、現地で働く日本人の方にお話しを伺うなど、海外の大学での学びや仕事について考え、将来へと繋げるきっかけを与えている。この海外経験は、英語学習の意欲を高める効果も発揮しているようだ。ほか希望制のターム留学などの制度も充実している。
「Liberal Arts教養教育プログラム」は、「学問(リベラル)」と「技能(アーツ)」との融合。「人間力」「キャリア」「実践体験」「ロジカル・シンキング」の4つの柱から成り立っている。
「人間力」とはコミュニケーションスキルを向上させること。共感力、人との距離の取り方を学ぶ。SNSモラルも学習する。「キャリア」は、自身の将来に向けて、キャリア形成をしていく。職業体験や職業ガイダンス、卒業生や民間企業で働く方の講義などで、将来について考える機会を与えたり、大学の学部・学科の学びの理解を深めたりという企画を実施。「実践・体験」は、日本を知る学び。フィールドワークとして、東京下町巡検(高1)や奈良京都への修学旅行(高2)ほか平和学習研修もある。「ロジカル・シンキング」は、論理的思考力を深めることが目的。物事を論理的にとらえ、相手に伝える方法を学ぶ。ディベートや論文など様々な形で授業を行う。
施設設備
眺望が素晴らしい図書室は生徒に人気
10ヘクタール以上の広大な敷地があり、大妻女子大学と併設されている同校。グラウンドは、人工芝グラウンド(共用グラウンド)と天然芝グラウンド(中高グラウンド)、土のグラウンド(球技場)と3つある。夜間照明も備わったテニスコートが6面、体育館は3つある。実験室は、化学と生物用に4室、物理用に1室、計5室。3つの英語学習室(call教室)は、備え付けPC・タブレットや、リスニング用のソフトを使った先進的な授業が展開できる最新設備を整えている。茶道部の活動や茶道の授業を行う和室もある。
生徒に一番人気の施設は図書室と約200席ある自習室。眺望のいい場所にあり、木を基調とした、吹き抜けのある広々とした気持ちのいい空間。午後7時まで利用可。
学校行事
中高の生徒が一致団結する体育祭・文化祭・合唱祭
「体育祭」「文化祭」「合唱祭」が三大行事。6月に開催される「体育祭」は、各学年を縦割りにし、中学1年から高校3年まで4つの色に分かれてチームを組む。上級生と下級生の交流が活発に行われ、お互いの応援を通して学年を超えた一体感が得られるイベントだ。9月に行われる文化祭「欅祭」は、中高全員の生徒が一致団結して盛り上げる。展示物、イベント、屋台などが学園通りにズラリと並ぶ様子は圧巻。(2020年、2021年はオンラインで開催)。「合唱祭」は1月または2月開催。プログラムは中学と高校分かれ、それぞれクラスが選んだ楽曲を披露する。
部活動
中学1年は全員がクラブ活動に参加
同校のクラブ活動は、中学と高等学校が一緒に行う。中学1年はクラブ活動必須。部活動を通して、先輩たちとの縦の繋がりをスタートさせ、クラスメイト以外の生徒との交流を持つきっかけづくりをする(中学2年からは任意)。全国区の強豪クラブを目指すというより、楽しくクラブ活動をすること、そして目の前の試合に勝利するために全力をつくすことを目標にしている。バトン部、ラクロス部は全国大会の常連校。
進路指導
生徒一人ひとりに手厚く進路指導
同校は1学年、160名ほどと小規模だが、その分、一人ひとりの生徒に対し手厚いサポートを行っている。「大妻多摩の進路指導は、一人ひとりの夢の実現のサポート」としており、中高6年間を通して、生徒の知的好奇心を刺激し、学習習慣を身につけていく。大妻多摩の進路指導は「進路の個別最適化」を重視している。
担任だけでなく、教科担当も協力して、生徒が目標を達成できるように情報を共有して指導を徹底。その成果は合格実績に現れており、2023年は北海道大学、東北大学、横浜国立大学、東京農工大学など、国公立の難関大の合格者を出している。また推薦入試による受験も増えており、およそ3分の1の生徒は推薦入試で進路決定をしている。そのため、論文の添削などのサポートも丁寧に行っている。指定校推薦枠は、早稲田大学、慶応大学、上智大学、東京理科大学、明治大学ほか、GMARCH以上の難関大も多い。
その他
生きる力の土台となるキャリア教育
学祖大妻コタカの教えに「らしくあれ」という言葉がある。人間がそれぞれの成長過程に応じた考え・態度・行動を取る、という意味だ。中高生は中高生らしく、社会人は社会人らしく、人間は自分の立場を鑑みることで自分を再認識する。生徒の成長を促し、一女性として経済的・社会的・人間的自立を達成させるために、大妻多摩では「らしくあれ」の精神に基づいたキャリア教育を実施。自分の適性を見極め、他とは違う自己を形成し、学問を通して自分の力を高めた上で、未来社会の中で未来世代のために貢献できる女性を育んでいる。
中学1年時に自分史を書いて中学受験合格までの人生を振り返り、中学前までと中学入学後の自分を比較することで自分の成長過程を確認。その後中学2・3年時には職業調べや職業ガイダンスを通じて自分に適した学問やキャリアを考え、将来の自分の姿を思い描いていく。高校では「卒業生を囲む会」で卒業生から与えられる直接のアドバイスや、保護者、特に生徒の父親が主体となって運営する「おやじの会」メンバーが行う職業ガイダンスで得られるキャリアの知識が大きな刺激となる。
その他、希望者対象のイベントが多く実施されることも生徒のキャリア形成に役立っている。東北被災地訪問、裁判傍聴、有識者による講演会等を自分の時間を使って、自分の脚をはこんで情報を取りに行くことで深い学びとなり、自分の適性に合ったキャリア選択を考える際の一助となる。
制服
伝統ある清楚なセーラー服
制服は白と紺を基調とした伝統的なセーラー服。中学生はネクタイ、高校生はリボンタイを着用する。ネクタイには、かつての大妻多摩生がデザインした「OTの文字と学園通りにある欅の木の葉」のエンブレムが刺繍されている。
2025年度からスラックスを制服に導入。季節に対応しやすいパンツスタイルとなっている。夏用・冬用があり、生地の厚さが異なる。従来の制服に合わせても違和感のない、洗練されたデザインに仕上がっている。
セーターは暖かい時期は白、涼しい時期には紺があり、冬に着用するコートはピーコートとダッフルコートが選択可能。