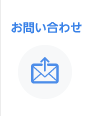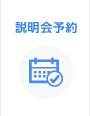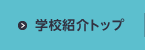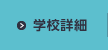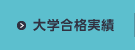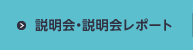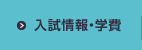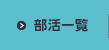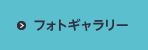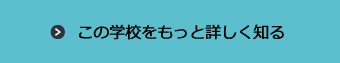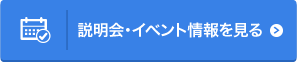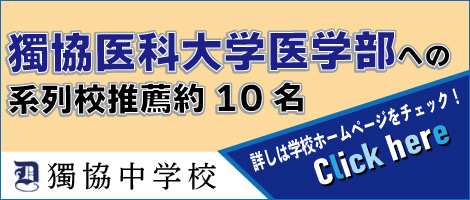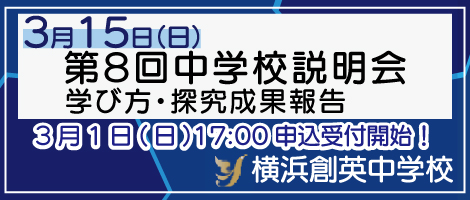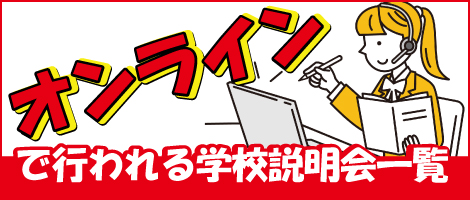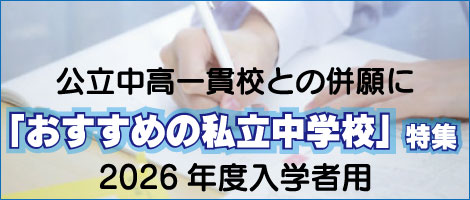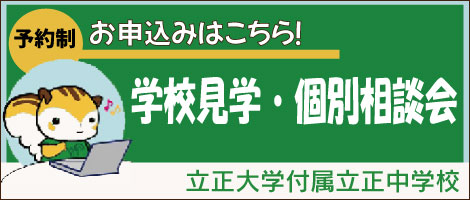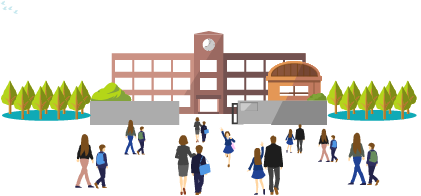スクール特集(明治学院中学校の特色のある教育 #8)

成功の秘訣は「自分から動く」! 「人間力」を磨くターム留学
明治学院中学校・東村山高等学校では、2024年度からターム留学プログラムがスタート。ニュージーランドで約3ヶ月間過ごし、4月に帰国した生徒の成長ぶりを取材した。
明治学院中学校・東村山高等学校では、50年以上前から国際交流プログラムを推進してきた。これまでも、アメリカでクリスチャンの家庭に滞在する「40日間ホームステイ」(高校生対象・選抜希望制)といった同校独自のプログラムを実施してきたが、2024年度から「ニュージーランドターム留学」が新たにスタート。プログラムの目的や内容について、英語科の曽武川道子先生とターム留学に参加した生徒に話を聞いた。
ターム留学で磨く「人間力」
同校では、2024年度から3つの国際交流プログラムがスタートした。「オーストラリア・スタディツアー8日間」と「イギリス・スタディツアー10日間」は中3から高3の希望者を対象とし、異文化体験を主な目的としている。どちらも、夏休み中に部活動がある生徒も参加しやすいショートプログラムだ。一方、高1と高2の希望者を対象とする「ニュージーランドターム留学」は1月下旬~4月上旬までの約3カ月間、1家庭に1人でホームステイをしながら現地校に通うプログラムとなっている。
「2024年度は高1が5人、高2が9人参加して、ニュージーランドの首都・ウェリントン周辺の7校(1校に2人)に通いました。スタディツアーとターム留学は、目的が全く違うプログラムです。ターム留学は、約3ヶ月間現地校に通って現地の生徒たちと一緒に勉強するので、観光気分で行くプログラムではありません。現地校での学びへの姿勢が大切になるので、参加するためには英語力(英検準2級以上)だけでなく、前年度の欠席と遅刻の回数にも基準があります」(曽武川先生)
スタディツアーが異文化体験を主な目的としたプログラムであるのに対して、ターム留学は「人間力」を磨くことを目指したプログラムとなっているという。
「ターム留学は、問題解決力やコミュニケーション力、視野を広げることなど、人間力を磨くことを目指しています。ホームステイや現地校での生活を通して人間力が磨かれていく中で、英語力の向上という成果も付いてくるのです。3ヶ月の間、ただ現地校に通って授業を受けるだけではなく、事前にテーマを決めて探究活動にも取り組みます。SDGsの項目と関連したテーマを決めて、事前学習としてどのようなことを調べたいかプレゼンを行い、帰国してから現地で調べた結果を発表します。2024年度に参加した生徒たちは、それぞれに成長して帰国しました。3ヶ月は長いようであっという間なので、参加した生徒たちからは『もっとニュージーランドにいたかった』という声が多かったです。高1と高2からスタートさせましたが、将来的には中3にも機会を広げることも検討しています」(曽武川先生)

▶︎英語科 曽武川道子先生
高校2年次にターム留学を経験した生徒にインタビュー
Mさん(高3 英検:2級)
Kさん(高3 英検:準1級)
――ターム留学をしようと思った理由を教えてください。
Mさん 2年前の夏に「アメリカ40日間ホームステイ」に参加して、異文化体験をしました。そのときは、ホストファミリーとコミュニケーションを取りながら、日本とアメリカの違いを知ることができてよかったと思っています。ターム留学はニュージーランドの現地校に通って同年代と交流ができるので、違う形でよい刺激が受けられると思って参加しました。
Kさん 私は将来、好きな英語を使って仕事をしたいと思っています。日本で過ごしているだけだと、家と学校と塾の往復で高校生活が終わってしまいそうだったので、他国の高校でいろいろな経験がしたいと思って参加しました。高3に向けて受験勉強に集中したいという思いもあって悩みましたが、参加してよかったです。

▶︎Mさん
――ターム留学を経験して、どのような変化がありましたか?
Mさん ニュージーランドで友達とよい関係を築いて、現地での生活にも慣れてから帰国したら、逆カルチャーショックを受けました。日本と比べて明るくてフレンドリーな人が多かったので、自分には海外の方が合っていると感じています。現地の友達に日本のイメージを聞いたら、コンビニでの接客が「いらっしゃいませ」「ありがとうございます」など、完全にパターン化されていていAIのようだと言っていました。ニュージーランドでは相手の調子を聞いたり、日常会話から始まるので、客と店員ではなく人間同士の会話という感じです。日本はコールドカルチャーで海外はウォームカルチャーという印象を持たれていることを、外に出てみて感じました。
Kさん 日本では私立の学校に通っているので、家庭環境などが似ている人が集まっています。ニュージーランドでは公立高校に通ったので、他国から来ている人やずっとニュージーランドで暮らしている人など、いろいろなバックグラウンドの人がいました。例えば週末に友達と遊びたいと思っても、宗教的断食をするという人もいて、日本にいるときのように気軽に誘えない場合もあります。相手は自分と同じ状況ではないことが多いので、相手の立場になるという想像力が必要です。そのことを頭に置いて話すようになり、帰国してからも相手の立場を想像してコミュニケーションを取るようになりました。

▶︎Kさん
――英語力や学習意欲の変化は感じましたか?
Mさん もともと洋楽や洋画が好きで、学校の授業では習わないスラングなどを調べていたので、現地で実際に使ってみました。スラングは格好いいなと思っているので、使ってみたかったんです(笑)。アメリカでのホームステイや英会話教室でアメリカ英語に慣れていましたが、ニュージーランドはイギリス英語で、独自の訛りもあったりして違いが面白いなと思いました。ニュージーランドの人たちのようなアクセントに挑戦してみようという気持ちになったり、ニュージーランドの音楽を知りたいと思うようになり、興味も広がっています。
Kさん 行く前に英検準1級を取得していたので、会話にはそれほど困らないと思っていましたが、現地では留学生の中でも日本人留学生の英語力の低さが有名で悔しかったです。帰国してから、ニュージーランドの友達と電話をしたり、現地で撮影した動画を家族に見せたら、学校で習った例文を音読するときはトーンが一定だったのに、会話だと感情が入って抑揚が付いたねと言われたので、英語力の面でも成長を感じています。

――留学中に苦労したことはありますか?
Kさん ホストマザーが放任主義で、食事も朝と昼は自分で用意していました。夕食と掃除以外は、全部自分でやらなければならなかったのです。家に1人でいることも多く、独り暮らしのような感じでした。それは予想していなかったことですが、そのような状況を経験したことで人間力が上がったと思います。休日にホストマザーがどこかに連れて行ってくれることもなかったので、自分で何をするか決めて行動する必要がありました。自分から動かないと、何も始まらないのです。友達を誘って出かけたり、学校帰りに海に行ってみたり、スーパーで買い物をしてみたり、自分で留学を成功させていくことを考えていくうちに人間力が高まったと思います。初めての国だったので、どのお店で買い物をしたらよいかなど、一般的な生活についても友達に聞いたり、他の人の様子を見たりして参考にしました。
Mさん 僕も、留学を成功させるために自分から積極的に行動したから、よい経験ができたと思います。僕は小学生の頃からラグビーをやっていたので、現地でタッチラグビーのクラブチームに入ろうと考えました。Webサイトから申し込みをしたのですが、すでにチームができ上がっていたので、自分で新しくチームを作るか諦めるしかない状況でした。どうしようかなと悩んだのですが、通っている学校にもチームがあるとわかったので思い切って聞いてみたら、仲間に入れてもらうことができたのです。そこから友達も広がったので、自分から積極的に行動することが大切だと実感しています。試合にも出ることができ、2位のメダルももらえたので、とてもよい経験になりました。


――どのようなところにニュージーランドらしさを感じましたか?
Mさん 先住民のマオリ、インド系、その他のアジア系など、いろいろな民族がいます。ショッピングモールのフードコートも、ニュージーランドの料理だけでなく、インド料理や多国籍料理などが多く、日本と比べて多国から移民の受け入れが進んでいることが生活の中で感じられました。ホストファミリーにオールブラックス(ラグビー)の試合に連れて行ってもらい、マオリの伝統であるハカを生で見ることができたのも嬉しかったです。
Kさん 私も「アメリカ40日ホームステイ」を経験しているので、最初の頃はアメリカの方がフランクで、他国の人を受け入れやすいと感じました。私が通った学校では、ニュージーランドの生徒たちのグループと移民グループに分かれていて、常にそのグループで遊んだり行動しています。ニュージーランドグループに自己紹介したら、英語の発音を笑われたこともあり、外国人に対する壁を感じましたが、過ごしていくうちにそれはお国柄というよりは人によるのかなと思いました。
――現地ではどのようなテーマで探究活動をしましたか?
Mさん 僕のテーマは「多文化共生」です。いろいろな国から来た人が暮らすニュージーランドでは、どのように外国人を受け入れているか、政策や対策などを調べました。フードコートで提供されている料理をはじめ、ニュージーランドでは生活の様々な場面で「多文化共生」が感じられます。現地校でできた親友がドイツ人だったので、ドイツの移民問題についても聞きました。ドイツでは、移民が入ってくることは認めているけれど、仕事もしないで手厚い社会保障を目当てに入ってくる移民には反発している人が多いそうです。
Kさん 私は、「人や国の不平等をなくそう」をテーマにしました。留学生を中心に、いろいろな国の人と話しましたが、留学に来るときの費用の違い、学校で学べる言語の数などが興味深かったです。日本以外からの留学生は、英語以外にも、ほぼネイティブレベルで他言語を習得している人が多くいます。例えば、イタリア人留学生は英語、フランス語、ドイツ語も少し、ドイツ人留学生は英語、モンゴル語、イタリア語、フランス語、日本語も少し話せました。日本では、進路に直接関係ない教科も何年か学びますが、多国では早くから選択科目となっていて、得意分野を伸ばせるカリキュラムになっています。日本も早くから選択できるようになって、得意分野を伸ばせるようになるといいなと思いました。
――進路についてはどのように考えていますか?
Mさん 小さい頃からパイロットになりたいと思っているので、一般選抜や総合型選抜で他大学のパイロット養成コースを目指します。
Kさん 具体的な職業はまだ決めていませんが、指定校推薦で他大学を受験します。国際学部のコミュニケーションを学べる学科など、いろいろなことを学びながら職業選択につなげていけるような学部に進みたいです。

――受験生にメッセージをお願いします。
Mさん この学校は、「アメリカ40日間ホームステイ」や「ニュージーランドターム留学」など、英語に関するプログラムがいろいろとあり、異文化へ積極的にアプローチできます。将来、英語を使う仕事に就きたいと思っている人には、よい経験になると思います。
Kさん 異文化体験などのプログラムが充実していることが、この学校の魅力です。私は英語が好きなので、いろいろなプログラムに参加しました。英検などの試験を受けるときも、先生方が必要なサポートをしてくれます。私はライティングを強化したかったので、テーマ出しや添削をお願いしました。放課後には1対1で面接の練習をするなど、自分に必要なことは何か考えてお願いすれば、様々な形で対応してもらえます。
<取材を終えて>
インタビューした2人は、現地の公立高校に通って、ニュージーランドで暮らす人や様々な国からの留学生と交流し、日本で同校に通っているだけでは触れることのない価値観にも触れることができた。2人に共通していたのは、「自分から動かなければ何も始まらない」ことに気づいて行動できたことだ。英語や異文化に興味のある受験生は、海外プログラムの行き先や期間だけでなく、目的や成果にも注目していただきたい。
この学校のスクール特集

イギリスとオーストラリア、2つの海外研修プログラムがスタート
公開日:2024/10/17

様々な「出会い」を通して成長していく生徒たち
公開日:2023/6/12

広大なグラウンドで育まれる「自主性」。教育ツールとしてのラグビーの魅力
公開日:2022/4/26

調和と感謝を受け継ぎ“学校の顏”として活躍するハンドベル部
公開日:2021/6/23

礼拝から1日が始まる キリスト教に基づく「人づくり」
公開日:2020/7/13

聖書ゲームや賛美バンドも企画。 キリスト教理解への生徒主体の活動
公開日:2019/7/23

蔵書数6万4000冊、図書館は様々な交流が生まれる学びの場。
公開日:2018/7/6