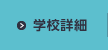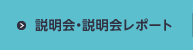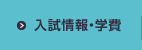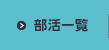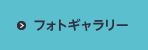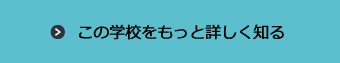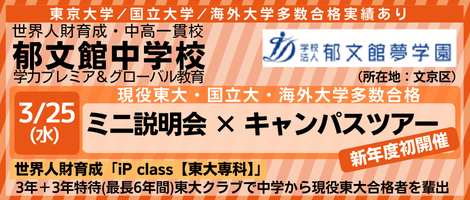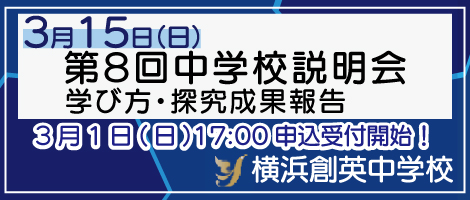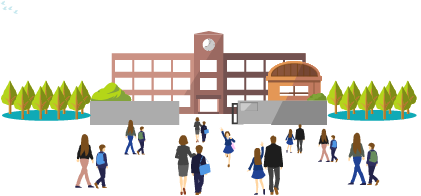スクール特集(山脇学園中学校の特色のある教育 #4)

研究活動を軸に「総合知」を育む、「サイエンスクラス」がスタート!
2022年度から、高校で「サイエンスクラス」がスタート。総合知を育む「サイエンスクラス」の特色とは?
2010年に「山脇ルネサンス」を宣言し、理想とする教育の実現に向けて進化を続けている山脇学園。「アイランド」と名付けた教育施設を活用しながら、これからの時代に求められる創造的な学力を育んでいる。2022年度から高校でスタートした「サイエンスクラス」について、教頭の鎗田謙一先生、情報科・理科担当の黒木和樹先生、サイエンスクラス担当の大島悠希先生に話を聞いた。
2022年度からスタートした「サイエンスクラス」
2010年に「山脇ルネッサンス」を宣言し、2011年に「サイエンスアイランド(SI)」と「イングリッシュアイランド(EI)」、2013年に「リベラルアーツアイランド(LI)」と名付けた教育施設を新設。理想とする教育の実現に向けて進化を続ける同校は、2022年度から高校で「サイエンスクラス」(希望選択制)をスタートさせた。
「中3で取り組む科学研究チャレンジプログラム(希望選択制)に続くクラスがあれば、4年間継続して探究活動できると考えて、高校にサイエンスクラスを設置しました。科学研究チャレンジプログラムの参加者は、ロボット・プログラミング・生物(動物・植物)の研究グループに分かれて、研究活動を1年間継続して行います。今までは、SI部としてそういった活動を続けることはできましたが、今年度からは学校のカリキュラムとして整備して、6年間という道のりの中で取り組めるようになりました」(鎗田先生)
同校は、2021年度に校長に就任した西川史子先生を中心に、これまで以上に主体的な学びを推進。6年間の教育全体についても総点検していると鎗田先生は説明する。
「これまで、アイランドを活用したアイランド教育に力を入れてきましたが、昨年度からは総合知*をコンセプトとしたカリキュラムへと進化させています。高1でスタートしたサイエンスクラスは、総合知という考え方に合ったやり方で出発しています。ですから、サイエンスクラスでの手応えをもとに、6年間すべての活動を編成しなおしているところです。サイエンスクラスで主体性が育つことがわかったものは、他の学年にも取り入れていくなどさらに進化させていきます」(鎗田先生)
*「総合知」とは、自然科学の「知」や人文・社会科学の「知」を含む多様な知を総合的に活用し、知の活力を生むこと。文部科学省はSociety 5.0の実現に向けて、「総合知」の活用を推進している。

▶︎ 教頭 鎗田謙一先生

空間や時間を広げて物事を見る力
「サイエンスクラス」は、研究活動の継続だけでなく、社会に出てから科学技術を使って活躍できる女性を育みたいという思いもコンセプトの1つだと、大島先生は説明する。
「理学・工学・情報学といった社会進出に偏りがある分野に、女性が進めるようにすることも女子校の果たす役割の1つだと考えています。社会に出てから新たな観点で様々な提案をするためには、幅広い視野で物事を見られる力が必要です。サイエンスクラスでは、大学教授を招いた宇宙に関する講演会や、富士山での校外学習なども行っています。富士山では、研究者の方に同行していただいて樹海探索をしたり、展示室で宝永噴火の噴出物のはぎとり標本(実物の積み重ねで再現したもの)を観察したりしました」(大島先生)
宇宙や富士山について学ぶことは、空間や時代の感覚を広げて物事を見ることにつながる。例えば、江戸時代や平安時代の噴火については、地学的な観点だけでなく、社会に与えた影響などからも学ぶことが多いという。
「校外学習では、富士山を通して、過去の仕事、今の仕事、未来の仕事についても考えました。例えば、新幹線に乗ると熱海と三島の間に長いトンネルがあります。このトンネル工事によって大量の地下水がトンネル内に抜けてしまい、トンネルの真上に広がる丹那盆地では水田などに使われていた水が枯れてしまいました。そのため、稲作から酪農に転換し、今では伊豆でも有数の酪農地帯となっています。このような背景を知らなければ、ただ牧場に行って『アイスクリーム、美味しいね!』で終わってしまうかもしれません。1つの仕事が及ぼした影響まで見ることは、科学者を育てていく上で大事なことだと考えています」(大島先生)
校外学習では、なぜそこに行ったのか、自分はどのように感じたのかなど、哲学をしていく部分も大事であると、大島先生は語る。
「自分について語れることが、成長につながると考えています。サイエンスクラスでは、いろいろなことにチャレンジしていきます。教員が用意していくのではなく、生徒たちが自分の琴線に引っかかるものに飛び込んで、様々な人やものと出会っていくのです。例えば、森林の研究をしたいという子は、コンクールに応募して岡山まで足を伸ばし、現地の職人に話を聞き、そこから大学の先生を紹介してもらうなど、ビリヤード台ではじかれた球のようにいろいろな人脈につながっています。教員が用意する出会いではなく、自分たちで動くことが様々なご縁につながっているのです」(大島先生)。

▶︎サイエンスクラス担当 大島悠希先生

生徒たちの主体性を引き出す「待ち」の姿勢
同校では、教員の専門分野からテーマを選ぶというような枠を決めることはせず、子どもたちの主体性を大切にしていると黒木先生は説明する。
「子どもたちはみんな、やりたいことをおぼろげに持っています。もともとやる気があるのですが、大人が『それはダメ』などと制限や枠を作って壊してしまうのです。やる気を壊さないためには、教員にとってはジレンマですが『待ちの姿勢』が大事だと思います。先日も、テーマをずっと考えていた生徒がやっと『アブラナ科の植物が持っている辛み成分の抗菌作用』について調べると決めました。彼女が『計画を考えるのは楽しいですね!』と言っていたのが印象的でした。目の前で行われている作業が遠回りに感じても、小さな失敗も経験の場とみなして時々声がけはしながら温かく見守るようにしています。たとえ失敗しても、次にもう一度立ち上がって挑戦すればよいのです。放任ではなく、子どもたちがやりたいことに挑戦できるようにサポートする体制を整えて見守っています」(黒木先生)
休みの日にも調査に行くなどどんどん主体的に行動している生徒もいる。一方で、迷ってしまい前に進めない子もいる。そんなときは声をかけて、一歩を踏み出すために背中を押しているという。
「1人あたり1万円の研究費が使えますので、3人で研究を進めれば1つの研究に3万円使えることになります。限られた予算の中で必要なものを買わなければならないので、例えばロボットを作るパーツを買うときなどに、迷ってしまう子もいるのです。迷っているのがワッシャーの素材だったりするので『水を使うなら錆びないものがいいよ』などのアドバイスはしてあげます」(黒木先生)
「サイエンスクラス」では、科学コンクール、学会などへの参加を必須として活動を進めているが、教員はリストアップするだけでどれに参加するかは子どもたちに選ばせている。
「教員が決めるのではなく、自分たちで選んだ方がスケジュール管理も自分たちでできますし、モチベーションも高まるでしょう。高1といっても大人として扱った方が、社会性もより高まると思います。自分のことは自分で決め、決めたことは責任を持ってやり、やりたいことを見つけて挑戦できるように教員たちはサポートしていきます」(黒木先生)

▶︎情報科・理科担当 黒木和樹先生


「サイエンスクラス」での生徒の変化
「サイエンスクラス」がスタートしてから約半年が過ぎ、生徒たちの行動力やエネルギーに驚かされることも多いと大島先生は語る。
「生徒たちの行動力はすごいと実感しています。例えば、野球が好きなある生徒は、通っている塾が入っているビルに大学野球の事務所があることがずっと気になっていたそうです。そして自分から事務所を訪ねたり、大学へ行って選手と関わったりして『球場の硬さが選手の故障に及ぼす影響』という研究テーマにたどり着くことができたのです。彼女は、『先生聞いてください!』と嬉しそうに経緯を話してくれました。動き始めると、どんどん人との出会いがめぐってくることに感動しています」(大島先生)
引っ込み思案だった生徒にも、嬉しい変化が見られたという。
「ポスター発表をしていると段々と原稿を持たなくなって、身を乗り出して身振り手振りで説明するようになっていきます。きちんとリアクションが取れるようになり、1日で劇的に変化する様子を目の当たりにして、担任としてとてもありがたい気持ちになりました」(大島先生)

道具としてのデータサイエンス
「サイエンスクラス」では科学研究活動のほかに、研究活動を支える独自授業として「科学英語」と「データサイエンス」を実施。「科学英語」では、先行研究を英語で読み、調べたことを英語で表現。「データサイエンス」の授業は、アクティブラーニング型の授業で進められる。
「情報の授業でデータサイエンスを学びますが、データサイエンスを学問にとどめるのではなく、道具にしたいと考えています。必要なツールは早い段階で与えて、他の授業で使える場面があれば使ってほしいです。数学や英語でも言えることですが、学問にとどめていては道具として使えません。授業の中で使える場面を想定して、必要な時期に必要なスキルを与えたいと考えています」(黒木先生)
情報の授業では、統計処理の出来上がったエクセルファイルを渡すのではなく、自分たちで統計処理を行えるようにすると黒木先生は説明する。
「データを貼り付けるだけで結果が出るパターンだと、社会に出てから本当に必要なものを自分で作れるようにはなれません。本校では、プログラミングと統計をセットで教えています。教員が1からやり方を教えるのではなく、テキストを1冊渡して『わからなかったら質問する』スタイルです。わからないことは教員や友達に聞いて、協働力や主体性を育みながら統計やプログラミングに挑戦していきます」(黒木先生)
今年度の後半には画像解析にも取り組む予定だが、すでに画像処理を研究計画に取り入れている生徒もいるという。
「屋外実験場で飼育しているカワリヌマエビを使って、色を見分けているかという色覚の実験などを行っている生徒がいます。カワリヌマエビが色に反応しているかを調べるためには、四六時中見ていなければなりません。実際にずっと見ているわけにはいかないのでビデオで撮影しますが、それをチェックするのも大変な作業です。プログラミングを使ってパソコンに解析させる方法があり、情報の授業でもやる予定だとわかると、早くやりたいと言ったのです。ビデオをチェックするよりも、楽に見えたのでしょう。楽をしたいという気持ちからであっても、彼女自身が自分でプログラミングを覚えたいと思ったことが重要なのです」(黒木先生)
教科の枠を越えることの重要性
英語やデータサイエンスなどを道具として使うためには、教科の枠を越えることが重要だと黒木先生は語る。
「情報の授業で学んだことが授業の中だけで完結すると、他とのつながりが見えません。例えば、富士山での校外学習でデータを取りますが、事前学習として生物の授業で生態系について学びます。その知識を持ってデータを取って、情報の授業でそれを分析してグラフを作ります。そして、科学英語の授業では調べたことを英語で表現するなど、教科の枠を越えて高めていくことができるのです」(黒木先生)
教科の枠を越えるために、研究活動が大きな役割を果たしていると、大島先生は語る。
「研究活動という主路線があることで、その周りにあるものをつなげることができます。研究活動がなければ、勉強してテストで点数をとるために頑張るという、1つ1つが独立した存在になってしまうでしょう。自分が研究していることをもっと発展させるためにはどうすればいいか考えることが、点と点をつなげます。中心に自分の研究があるからこそ、つなげていくことができるのです」(大島先生)

保護者からも共感の声
「サイエンスクラス」が目指す学びについては、多くの保護者から共感を得られているという。
「保護者面談でも、共感してくださる方が多いです。社会に出てからは、自分たちで模索して、人とつながって答えを見つけていきます。保護者の皆さんも、今の時期にそのような体験をしておいた方がよいと考えているようです。特に、お父さんと面談をするとそのような考えをされている方が多いと感じます。大学受験でも、このような力を認めてもらえる総合型選抜などが増えていますし、このような力は今後ますます必要になってくるでしょう」(大島先生)
「サイエンスクラス」での経験を通して、学び方や大学の選び方も変わってくるだろうと黒木先生は語る。
「何かをしたいという目標をしっかりと持って、進路選択をするようになるでしょう。これをしたいからこの大学へ行きたいなど、内発的な動機付けにつながるので、学び方の姿勢も変わっていくと思います」(黒木先生)
<取材を終えて>
「サイエンスクラス」での研究活動が、データサイエンスや英語、歴史など、様々な分野をつなぐきっかけになっているという話が印象的だった。自分と何も関係のない英語の論文を出されても、なかなか読む気にならないだろう。しかし、先行研究が英語で書かれていたら、頑張ってそれを読もうという気持ちになる。データサイエンスの場合も、自分の目でチェックする大変さがわかっているから、画像解析を覚えようという気持ちにもなるのだ。「サイエンスクラス」での成功事例は、他の学年にも広げていくという。来年度以降も、どのように進化していくか注目していただきたい。