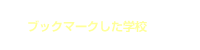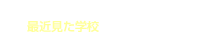スクール特集
![]()
”未来の科学者”の芽を発掘し、育てる
「つくばScience Edge サイエンスアイデアコンテスト」
 学校での研究をもとにして科学に関する「アイデア」を発表するコンテストに、広尾学園高等学校の生徒たちが参加しました。
学校での研究をもとにして科学に関する「アイデア」を発表するコンテストに、広尾学園高等学校の生徒たちが参加しました。
発表の舞台は、世界の科学者が集う拠点となっている「つくば国際会議場」。
日ごろの研究を外に向かって広く発信するまたとない機会に、生徒たちはどのように臨んだのでしょうか。
開催日の2013年3月23日、広尾学園に同行し、コンテストの模様を取材しました。
※「つくばScience Edge サイエンスアイデアコンテスト」について
主催:つくばScience Edge2013実行委員会
共催:株式会社JTBコーポレートセールス
後援:独立行政法人科学技術振興機構(JST)、茨城県、つくばサイエンスアカデミー
2010年よりスタートしたこのコンテストは、国内外の中高生を対象に“サイエンスアイデア”を募集します。応募要件は、授業の課題研究やクラブ活動での研究をもとに、生徒自らが考えたアイデアであること。研究アイデアが実現できるかどうかは問わず、夢のあるエッジの効いたアイデアであること。チーム参加・個人参加いずれも可。
 “サイエンスアイデア”を競い合うという、研究の成果そのものよりも創造性を評価するユニークなコンテストについて、つくば国際会議場館長でサイエンスアイデアコンテストの審査員を務めるノーベル賞物理学者・江崎玲於奈博士は、次のようにメッセージを寄せています。
“サイエンスアイデア”を競い合うという、研究の成果そのものよりも創造性を評価するユニークなコンテストについて、つくば国際会議場館長でサイエンスアイデアコンテストの審査員を務めるノーベル賞物理学者・江崎玲於奈博士は、次のようにメッセージを寄せています。
「創造力こそ改革・進歩の原動力となって、人類文明を発展させ、今後も発展させるのです。皆さんのような若い方に、創造力をおおいに伸ばしていただきたいと思います」
主なプログラムは、オーラルプレゼンテーションによる「アイデアコンテスト」と、「ポスター発表」。その他のプログラムとして、企業や大学、研究機関による「サイエンスワークショップ」も開催。今年はインテル株式会社、日本・バイオ株式会社、日本科学未来館、独立行政法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)、お茶の水女子大学など14団体が参画しました。
広尾学園が参加したプログラム
 医進・サイエンスコース植物栄養学研究チームの高2(現高3)女子生徒の応募が「アイデアコンテスト」の書類選考を通過し、本選に臨みました。
医進・サイエンスコース植物栄養学研究チームの高2(現高3)女子生徒の応募が「アイデアコンテスト」の書類選考を通過し、本選に臨みました。
「ポスター発表」には、医進・サイエンスコースの高1~高2の生徒11人がチームに分かれ、6つの研究テーマで臨みました。
さらに今年は特別に、広尾学園高等学校のサイエンスラボにおいて培養しているマウスiPS細胞の展示・紹介も行われました。
また、インターナショナルコースの生徒が、海外参加校の生徒たちのサポート役を務めました。
「アイデアコンテスト」(オーラルプレゼンテーション)
 第3回となる今年は、「アイデアコンテスト」に全国の中学・高校から24テーマの応募がありました。
第3回となる今年は、「アイデアコンテスト」に全国の中学・高校から24テーマの応募がありました。
応募されたアイデアから書類選考を経て、選抜された8チームが3月23日の本選でオーラルプレゼンテーションを行いました。
出場した8チームは、いずれも高校生です。パワーポイントを使用して400インチのスクリーンの前で発表します。プレゼン能力も高く、それぞれ創意あふれるアイデアを競い合いました。
プレゼンテーションは10分、審査員との質疑応答が5分。自分の研究について、その魅力を要点をつかんでわかりやすく伝える必要があります。研究テーマの一部を紹介しましょう。
| 学校名 | タイトル |
| 広尾学園高等学校 | 「シロイヌナズナにおけるカルシウム吸収に関わる遺伝子の解析」 |
| 茗渓学園高等学校 | 「3秒ルールの有効性を考える」 |
| 山形県立村山農業高等学校 | 「再発見:地域伝承ダイズ~青クルミ豆の復活を目指して~」 |
| 神奈川県立弥栄高等学校 | 「最古の合金―青銅鏡―を未来へ」 |
| 滝中学校・高等学校 | 「新型ペルチェ霧箱の制作」 |
広尾学園の研究発表
医進・サイエンスコース 玉村ドレミさんのプレゼンテーション
研究テーマ「シロイヌナズナにおけるカルシウム吸収に関わる遺伝子の解析」
玉村さんは、植物の生育について遺伝子レベルでの解明をめざすという、まさに先端科学の研究の成果と展望を発表しました。
 研究の背景には、近年脚光を浴びている植物工場があるといいます。
研究の背景には、近年脚光を浴びている植物工場があるといいます。
植物工場では、土壌汚染や天候の変化に左右されずに安定した収穫量が確保でき、無農薬野菜をつくることができるなど多くのメリットがあります。
一方、課題の一つとなっているのは、植物工場が人工的に生育条件を最適化して生長を促しているため、生長に必要とされるカルシウムが欠乏しやすいこと。
 そこで玉村さんは、分子生物学の研究材料としてもっともよく使われる植物のシロイヌナズナを用いて、カルシウム吸収における遺伝子の役割を研究。
そこで玉村さんは、分子生物学の研究材料としてもっともよく使われる植物のシロイヌナズナを用いて、カルシウム吸収における遺伝子の役割を研究。
この研究を続けることによって、カルシウム欠乏の原因を遺伝子レベルでつきとめ、さらに欠乏を防ぐ方法を解明し、提案したいと発表しました。
プレゼンテーションは落ち着いてわかりやすく、1人の研究者としての意思を強く持った、学会発表を見ているような印象でした。
 質疑応答では、審査員の先生が「先端的な研究をしていると感心した」と述べたうえで、この研究テーマを選んだきっかけを問うと、
質疑応答では、審査員の先生が「先端的な研究をしていると感心した」と述べたうえで、この研究テーマを選んだきっかけを問うと、
玉村さんは「野菜が好きで、おいしくて栄養もある野菜を食べたいと思いました。その栄養はどうなっているのかと、興味を持ったのがきっかけです」と答えました。
また西村暹博士(生物化学)からは、「参考文献に記されていた英語の学術誌はご自身で読んだのですか?」と質問を受け、
玉村さんは「はい」と自信を持って即答しました。彼女にとっては研究をするために英語の学術誌を読むことは当たり前のことであるからこその即答なのでしょう。
そのうえで西村博士は「こうした研究は高校生しての発表にとどめず、世界の研究者が投稿する学術誌などに発表し、広く社会に公開することを目指すといい」という高い評価とアドバイス。
玉村さんは「データが揃い次第、論文にまとめて世界に発信したいと思います」と抱負を語りました。
プレゼンテーション終了後、玉村さんに研究や将来の夢などについて話を聞きました。
 「私は研究が大好きです。自分の目標に少しずつ近づいていくことがとてもおもしろい。
「私は研究が大好きです。自分の目標に少しずつ近づいていくことがとてもおもしろい。
この研究も高1のときから2年かけて、やっとここまで来ました。
先生から分からないことは自分で調べなさいといつも言われます。そして私もできるだけ先生の力は借りずに自分でやるようにしています。
 研究には第一に粘り強さが必要です。そうした研究者としてのマインドを先生に教えられています。
研究には第一に粘り強さが必要です。そうした研究者としてのマインドを先生に教えられています。
研究は辛くてたいへんなこともある。失敗も重ねながら、やっと成果に結びつく。だから粘り強さが重要なんです。
おかげで学校の勉強に対しても、集中力がつきましたね。
医学部志望だったけれど、今は理工学部も考えています。ガンの研究や植物の研究とか・・・いろんなものに興味があります。今やっている研究は、学会で発表したり、学術誌に投稿したりするつもりで、これからもがんばって続けます」
ポスター発表
 「ポスター発表」(日本語または英語)では、応募した生徒がサイエンスアイデアや普段の研究活動の発表を行います。
「ポスター発表」(日本語または英語)では、応募した生徒がサイエンスアイデアや普段の研究活動の発表を行います。
今年は62校が参加。海外からは、タイ、中国、韓国計7校が参加しました。海外からの参加校は毎年増えており、今後も拡大する見込み。
すべての参加チームが展示会場にポスターを掲示し、閲覧して回る来場者たちの質問に研究チームの生徒たちが答えます。
そのやりとりは盛んで、会場はたいへんな熱気に包まれました。医進・サイエンスコースの生徒たちも、専門性の高い研究テーマを掲げてがんばっている様子が伝わってきました。
テーマ「有害排水を利用した光触媒水素発生システムの開発」
高2(現高3)の小林真由子さんの発表
水素燃料はクリーンエネルギーとして注目されていますが、水素を生産するには天然ガスなど化石エネルギーが必要であるため、完全なクリーンエネルギーといえません。
 このことに着目した小林さんは、化石エネルギーに頼らない光触媒反応による水素の生産システムについて研究しています。
このことに着目した小林さんは、化石エネルギーに頼らない光触媒反応による水素の生産システムについて研究しています。
「この研究は高1からずっと続けています。光触媒に興味があるので、これからも研究を続けていきたいです。
医進・サイエンスコースを志望したのは、研究活動ができると聞いたからです」
小林さんは真剣な表情でハキハキと答えました。
テーマ「伝染病の数理モデルの研究」
高2(現高3)の米津徳人さんの発表
インフルエンザなど伝染病の流行の仕方や、予防策について、数学の視点からアプローチしています。説明がとても丁寧で、態度も優しく、なんだかこちらが生徒になったような気になりました。
 米津さんは「将来は高校の数学教員をめざしています。教員はいろんな人と出会い、いろんな世界とかかわる必要があります。
米津さんは「将来は高校の数学教員をめざしています。教員はいろんな人と出会い、いろんな世界とかかわる必要があります。
そこでぼくは、研究活動ができ、しかもいろんな個性をもった人と出会える医進・サイエンスコースに入りました。
ここでは女子も男子も研究熱心で、先生と議論を戦わせている。
先生も社会人経験者が多く、いろんな経験をした人たちから学ぶことができます」
テーマ「生物の寿命を決定する要因の解析」
高2(現高3)の森下彩華さんと丸山梨乃さんの発表
「再生能力が高いことで知られるプラナリアは通常、無性生殖で殖えますが、生育環境が悪化すると有性生殖をするようになります。無性生殖を行うものは分裂で殖えるので、個体のとしての寿命が無いようにみえます。
一方、有性生殖によって殖えたものは個体としての寿命を迎えます。わたしたちは、同じ種で寿命があったりなかったりするこのプラナリアを用いて生物の寿命の起源に迫るべく、研究を進めています。」
 森下さんは「私は医師志望で、ガンの研究に興味を持ったのがきっかけで、寿命というテーマにたどり着きました。
森下さんは「私は医師志望で、ガンの研究に興味を持ったのがきっかけで、寿命というテーマにたどり着きました。
将来は臨床医を経たうえで研究医になりたいと思うようになりました。丸山さんといっしょに研究を続けていきたいです」
丸山さんは「将来は獣医志望です。研究はうまくいかないことも多いですが、本当に楽しいです。
論文をたくさん読み、知識も増えました。おかげで進路を選ぶ目も養われてきたと思います。大学を研究の中身から選ぶようになってきたからです。」
iPS細胞の展示・紹介
 別室の会場で、医進・サイエンスコースの生徒が培養しているiPS細胞を展示するとともに、生徒による細胞培養のデモンストレーションと、その体験会を開きました。
別室の会場で、医進・サイエンスコースの生徒が培養しているiPS細胞を展示するとともに、生徒による細胞培養のデモンストレーションと、その体験会を開きました。
生徒が学校で培養ているiPS細胞を持参し、顕微鏡で観察しながら、その特徴を概説しました。
培養のデモンストレーションでは、無菌操作の手法や継代培養、細胞凍結の手順などを紹介しました。実際の設備、器具を用いて、見学に訪れた人たちに細胞培養を模擬体験してもらいました。
会場には大勢の見学者が訪れ、大盛況。コンテストに参加した他校生徒たちも顕微鏡に接続されたモニターに映されたiPS細胞を熱心にのぞいています。特に細胞培養体験は大人気で、皆、楽しみながら興味深く取り組んでいました。
 海外参加校の先生や生徒も見学に訪れました。培養手順の説明は、広尾学園インターナショナルコースの生徒が通訳します。どちらも高1(現高2)で帰国生。
海外参加校の先生や生徒も見学に訪れました。培養手順の説明は、広尾学園インターナショナルコースの生徒が通訳します。どちらも高1(現高2)で帰国生。
理系志望という2人は、ネイティブと変わらない英語力で培養手順を丁寧に通訳し、海外生徒の質問に答えていました。
すでにお互いに友だちになり、打ち解けた雰囲気で話をする様子もみられました。
iPS細胞の展示・紹介を担当した生徒は笹原崇生さんと吉本楓さん。ともに高1(現高2)で、広尾学園中学校からの入学生です。iPS細胞の研究に取り組む二人に話を聞きました。
 笹原さんは今回の展示のねらいを生き生きと語ります。
笹原さんは今回の展示のねらいを生き生きと語ります。
「iPS細胞を実際に見てもらって、みんなに親しみをもってもらいたかった。iPS細胞って難しいものと思われがちですよね。
でもぼくみたいに普通の高校生が培養しているのだとわかれば、身近に感じられるのではないかと思うのです」
吉本さんは研究活動のやりがいを語ってくれました。
 「学校では毎日培養の仕事をしています。はじめは器具の取り扱いの練習だけでもすごくたいへんでした。
「学校では毎日培養の仕事をしています。はじめは器具の取り扱いの練習だけでもすごくたいへんでした。
培養の工程も、すべて頭に入れておかなくてはいけません。
分からないことは論文を検索して調べます。この1年間で自分はすごく成長したと思います」
 二人とも将来の夢は医師。
二人とも将来の夢は医師。
笹原さんは「iPS細胞の研究をしながら、医学部受験の勉強もしっかりがんばりたい。
研究によって考える力が身について、ふだんの授業への意識も変わりました」
吉本さんは「私はひとりの研究者としてiPS細胞を培養しています。片方で高校生もやっているんです(笑)。
それと部活はチアリーディング部だからチアリーダーもやったり(笑)。研究に慣れてきたから、同時にいろんなことをやっていきたい」
閉会式・表彰

閉会式では、「アイデアコンテスト」「ポスター発表」の表彰が行われました。
「アイデアコンテスト」は、日本を代表する科学者が審査を行い、創意指向賞、探求指向賞、未来志向賞の3賞が表彰されます。
審査員は、江崎 玲於奈博士(物理学)、岡田 雅年博士(物理学)、西村 暹博士(生物化学)、丸山 清明博士(育種学)の4名でした。
 「ポスター発表」は、投票によって日本語ポスターが上位3校、英語ポスターは上位2校が表彰されます。ポスターセッション審査員(研究者や筑波大学学生・大学院生など)をはじめとした来場者が投票しました。
「ポスター発表」は、投票によって日本語ポスターが上位3校、英語ポスターは上位2校が表彰されます。ポスターセッション審査員(研究者や筑波大学学生・大学院生など)をはじめとした来場者が投票しました。
「アイデアコンテスト」部門では、広尾学園の玉村ドレミさんが、みごと探求指向賞に輝きました。
審査員で生物化学を専門とする西村暹博士は次のように講評しました。
「野菜が好きだという自らの興味をもとに、難しい実験を着実に進めているのはすばらしい。玉村さんのように自分のアイデアを持ち、研究することはとても大事。学校もそれをバックアップしていることがよくわかった。今後も研究を続け、自分で英語論文を書いて国際誌の発表もめざしてほしい」
 玉村さんに受賞の感想を聞きました。
玉村さんに受賞の感想を聞きました。
「うれしい! 私の発表が審査員の先生方にどう受け取られるか心配だったけれど、評価してもらえてとてもうれしいです。
自分の研究を分かってもらうために、積極的に伝えていくことも大切だと思いました。これからもがんばって最後までやり遂げたいです」
閉会式は明るく、和やかな雰囲気に包まれていました。参加者全員が、それぞれ達成感と満足感を味わっているようです。みんなが互いにがんばりを称え合う温かい拍手で「サイエンスアイデアコンテスト」は幕を閉じました。
広尾学園 医進・サイエンスコースの研究活動
医進・サイエンスコースマネージャーの木村健太先生のお話
今回の「サイエンスアイデアコンテスト」参加のねらいについてうかがいました。
 「ねらいは大きく3つあります。1つは審査される方々が科学者であること。
「ねらいは大きく3つあります。1つは審査される方々が科学者であること。
研究者としての視点で研究発表を受け止め、ディスカッションを交わしてくれます。
高校生としてはすごいではなく、一研究者として的確に批評してもらえる。これはたいへん有意義な機会です。
2つ目に、アイデアに着目したコンテストであるということ。
中等教育での研究活動は、予算的にも設備的にも、研究に費やす時間の確保という面でも制約があります。研究の結果が得られていなくても、アイデアベースで勝負できることでサイエンスへの垣根が取り払われます。
 3つ目は、他校の生徒たちとの交流です。
3つ目は、他校の生徒たちとの交流です。
同年代の優れた研究に触れて、大いに刺激されることでしょう。
今後もこうした研究的な学びの機会を通じて、多くの生徒たちのこころに火がついてほしいと願っています」
研究活動について
生徒が7つの “研究カテゴリー”のいずれかに所属し、それぞれ自分のテーマを決めて研究活動を行います。チームや個人など、研究形態は自由です。
実験は学園新校舎に設置されたサイエンスラボで行います。生物・化学・物理&地学の3つのサイエンスラボがあり、大学研究室レベルの設備が整った環境で、中学・高校の枠にとらわれない実験が可能です。
研究カテゴリー
幹細胞生物学・植物栄養学・素粒子物理学・天文学・環境化学・数論・現象数理学
研究活動は休み時間や放課後を利用して、自分のペースで進めます。定期的にみんなで集まって経過を報告し、先生や仲間たちとディスカッションします。それを各自持ち帰り、研究に生かします。
各カテゴリーに担当教員がつき、生徒一人ひとりの相談に乗り、アドバイスしますが、研究の主体はあくまで生徒。教員から生徒に全てをレクチャーすることはできません。なぜなら先端研究の答えは教員自身知らないのですから。教員も生徒と同じ方向を向いて共に未知のテーマに立ち向かっています。